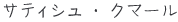2014年 3・4月号 No.283

ヴァンダナ・シヴァ
巨大主義(ジャイガンティズム)にとり憑かれたこの時代、我々は「ビッグ・イズ・ビッグ(大きいことが偉大だ)」という幻想の下に生きてきた。つまり、大きいことがより多くの生産を意味し、より強大な力を意味する、と。より広大な農場、大規模なダム、そして巨大な企業なしに、食料や水といった人類のニーズはまかなえないと、信じられてきた。事実、大企業はますます巨大化し、今ではたった5つの企業が種子と食物と水の供給元として世界に君臨している。
にもかかわらず、事実とは、生態学的にも、経済学的にも、政治学的にも、「スモール・イズ・ビッグ」、つまり小さいことこそが偉大なのである。
まず生態学的には、一粒の小さな種の中に、大きな木の可能性が生きていることを、私たちは知っている。また同じ一粒に、何千、何万の種を生み出す力が潜んでいることを。その何千、何万粒のそれぞれが、また何千、何万を生み出す力を秘めていることを。「豊かさ」とはまさにこのことだ。だからインドの農民たちは種まきしながら、「この種が尽きませんように」と祈るのだ。
しかし、豊かさの根源であるその種子を、巨大企業が知的所有権を通じて専有したり、ターミネーター技術によって次世代の種を生み出せないようにつくり変えたりする。種子をつくらない種子! 大企業の願いはこうだ、「この種が尽き、わが社の利益が尽きませんように」
種は私たちの食物となる。食の経済学も、まさに「スモール・イズ・ビッグ」だ。小規模の、生物多様性に富んだ田畑の方が、大規模農場よりも生産性が高い。それは我々がナヴダーニャ農場で証明してきたことに他ならない。(www.navdanya.org)
実際、種子の多様性を保存し、生物多様性をますます高めることで、収量も、収入も倍増させることが可能なのだ。農業におけるこの「スモール・イズ・ビッグ」は、しかし何も新しいことではなく、大昔から知られていた。それなのに、いつの間にか、「大きいこと」に食の安定供給を司る特権が与えられてしまったのである。
農業経済学者でもあったインドの元首相チャラン・シンも、小規模農場の方が大規模農場よりも生産性が高い、と言っている。・・・(中略)・・・インドだけでなく、世界中の食の安全保障は、小規模農家を保護し、支え、励ますことができるかどうかにかかっている。
大規模で工業的な農業より、小規模農業の方が生産的なのはなぜか? それは小規模農家の方が、土、植物、そして家畜に対してもっと細かい心配りができるから。そしてそのことによって生物多様性を高め、外からの化学的なインプットを減らすことができるから。農家の規模が大きくなればなるほど、労働力は農機具と、それを動かす化石燃料にとって替わられる。そして、農民の心のこもった仕事も毒性をもった化学物質にとって替わられることになる。面積あたりの収量は実際には下がるのだが、大規模農家の方がより生産的であるかに見せかけるために、ふたつの操作が行われる。
第一に、生産のためのコストとして労働力だけを勘定に入れることで、小農民やその家族の労働を省いて、化学肥料や農薬、機械などに置き換えることが正当化される。この偽りの計算方法によれば、これで生産性は上がったことになってしまう。いわば、小さき者を生贄にする悲劇から、「大きければ大きいほどいい」という神話が生まれる。そしてこの“神話”が飢餓問題の解決策として世界中に売り出されるというわけだ。
二つ目のトリックは、農家が生み出すすべての生産物を勘定しないで、一つの商品作物の収量だけを計算することだ。単一栽培(モノカルチャー)だけがまともな農業だという固定観念に囚われた心には、生物多様性が与えてくれる豊かな恵みが見えず、実際には遥かに低下した食糧生産でさえ、収量の増加と見えてしまう。
それに対して、我がナヴダーニャ農場は、「面積あたりの健康量」という基準を立てた。それによれば、農地における生物多様性が高ければ高いほど、そこから生み出される栄養価も高くなる。そして大事なことは、小規模な農家だけが高い生物多様性を保持できるということなのだ。
食に関しても、「スモール・イズ・ビッグ」こそが真理だ。大規模農場に注ぎ込まれている巨額な助成金にもかかわらず、また工業的な農業への転換を後押しする政府の様々な政策にもかかわらず。今でもFAO(国連食糧農業機関)によれば、全世界の72%の食料は、小規模農家によって生産されている。これに、全世界の庭先や空き地や市民菜園で行われているガーデニングまで含めれば、人々が今日食べているもののほとんどは、いまだに“小さな場所”で育まれていることがわかる。
大農場が作っているのは、食物ではなく商品だ。例えば、グローバル市場を支配するトウモロコシや大豆のうち、人間の口に入っているのは10%に過ぎない。残りは、バイオ燃料として車を走らせるのに使われたり、家畜工場の餌として、動物たちの口に無理やり詰め込まれている。ビッグな農業ではなく、スモールこそが世界を養っているのだ。ビッグはといえば、毒を世界中に撒き散らし、飢餓を増大させている。2013年のUNCTAD(国連貿易開発会議)が発表した2013年の「貿易と環境に関する報告書」には、こんなタイトルが付けられている。「手遅れになる前に目覚めよ——今こそ真に持続的な農業によって、気候変動の時代における食の安全を確保しなければならない」。同報告書によれば、単一栽培と工業的農法は、十分な低価格の食料を必要な人々に供給することに失敗している。そして、自然環境への負荷を増やし続けることによって、食の未来を脅かしている。
また報告書はこうも断言している。経済的に豊かな国でも貧しい国でも、農業は単一栽培から多品目栽培へと移行し、肥料などの投入を減らし、小規模農民への支援を強化し、食物の地産地消を推進すべきだ、と。
2012年のILO(国際労働機関)の報告書「持続可能な開発に向けて」もまた、小規模農業こそが、環境危機ばかりでなく、食糧危機や雇用の危機にとっての解決策でもあると述べている。そこには、いかにアフリカの小規模農家がエコロジカルな農業を手がけることによって収量をも増やした数々の例が挙げられている。例えば、ケニアの南部ニャンザにおける1000人の農家が参加したプロジェクトでは、オーガニック農業に転じることによって、平均2ヘクタールの農地で、1ヘクタール毎に2トンから4トン、作物収量が上がったという。また、同じケニアのティカでは、約3万人の小農民の収入がやはり有機農業への転換から3年で50%増えた。
・・・・(中略)・・・・
スモールは食物連鎖と水循環という自然の摂理にかなった“小ささ”のこと。スモールこそが自然を保全し、他の生物種の生存を保障し、人間にも食物や水という豊かな恵みを与えてくれる。これまで自然破壊を繰り返してきたビッグは、実はビッグでもなんでもない。真にビッグで偉大なのは食と水を私たちに与え続けるスモールの方なのである。