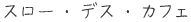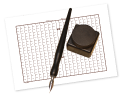人間の死は、臨床の場においては、死の三徴候(呼吸停止・心臓停止・瞳孔散大)の確認によって判定されているのが通例かと思います。しかし、死の三徴説による死亡判定は便宜上行われているに過ぎず、意外にも医学上の死の定義は明確ではありません。明確でないがゆえに、昨今では、臓器移植を前提として、脳機能の不可逆的喪失、いわゆる脳死を人の死とする向きもあり、これには重大な問題を含んでいるように思えます。
心臓、肺、脳機能の不可逆的喪失によって、生物としての機能を失うことが死だと、つい考えてしまいますが、それは死のひとつの側面でしかありません。
例えば、もしあなたが医師から余命告知を受けたなら、それをどのように受けとめるでしょうか。また、あなたの愛する人が臨終を迎え、火葬され、この世からその肉体が消えてなくなったとしたら、その人の存在も無になったとしか考えられないでしょうか。
生物としての機能を失う瞬間だけが「死」ではなく、人間が死を意識したときからその意識が消えてしまうまでのすべてが「死」である―「死は瞬間ではなく過程である」、まずはそのように考えたいと思います。
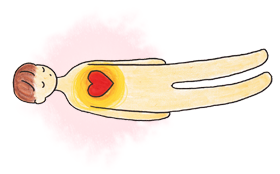
そもそも「死」は、文化、時代、分野、人によってさまざまな考えや解釈があり、上記のような臨床上の定義のみならず、死の定義はこの世界に存在しません。以前、倉本聰さんと食事をする機会があり、その時に倉本さんは、「死とは骨が土に還る瞬間」とおっしゃっていましたが、「死」とは多様なもの、概念を超えたものなのです。
死とはなにか? それは誰にもこたえられない、とらえどころのないものです。だからこそ、「死」について考えるのは尊い行為だと、わたしは思います。
とらえどころのない「死」ですが、それは例外なく訪れ、あらゆる生物はみな、いつか必ず死んで逝きます。誰もがいつか死んでしまうとわかっているのに、どこか、自分や愛する人が本当に死んでしまうとは認めていない、それが死を考える上でとても難しいことでしょう。
「死」について、辻さんは『ぶらぶら人類学』のあとがきに、次のように寄せています。
老いについて、死について思うときには下向き、後ろ向きにならざるをえない。少なくともぼくはそうだ。本書にも登場する精神障がい者のコミュニティ「べてるの家」の向谷地生良さんはよく「いのちの傾き」について語る。人はみな生まれたときから、死に向かってゆっくりと、かすかな勾配を下りていくのだ、と。…………
同じように、母の老いと病と死は、ぼくにとって最良の学びの場となった。今でも、あの月日を思うと、ぼくはある種の歓びに満たされる。もっと生きてほしかったという思いはもちろんある。でも、それをはるかに凌駕するのが、母とともにあの老病死を“生きる”、スローで穏やかな時間に恵まれたことのありがたさだ。
母の死を“生きる”ことで、ぼくはやっと一人前になれた気がする。表現に困るのだが、「生きていく覚悟ができた」とでもいった感じだ。「よし、死ぬまで生きていこう」、みたいな…。
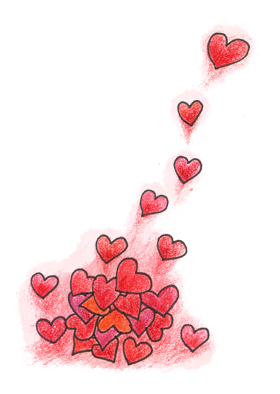
もしあなたが余命告知を受けたなら、きっと「生きたい」と気持ちになるでしょう。でも本当は、向谷地さんが言っているように、余命は生れたときから宣告され、いのちは下に向かってゆるやかに勾配しているのです。そして、あるとき、ひとつのいのちは終わりを告げます。いのちとは生と死である、と言えるでしょう。そして、辻さんが書いてくれているように、目の前で愛する人の死を見つめる経験は、辛く悲しい経験でありながら、与えられたこのいのちには限りがあり、いまを大切に生きることを思い出させてくれます。生に執着することなく、「死ぬ瞬間まで生きよう」と目覚めさせてくれるのです。
余命宣告をされなくても、愛する人の死を経験しなくても、ちょっと立ちどまって死について思いを馳せる時間を持つことは、自己の生に向き合う経験となるはずです。また、「いのちとはなにか」、「存在とはなにか」、「生物と無生物とはなにか」、「精神と物質とはなにか」などなど、根源的な問いにも思いが及び、学びの機会を与えられるでしょう。
そこまで哲学的に考えることはないにしても、「死とはなにか?」について考えることは辛く、悲しく、でもなんか元気が湧いてくる、そう思っていただきたいなと思います。
「スロー・デス・カフェ」のねらいは、まさにそこです。